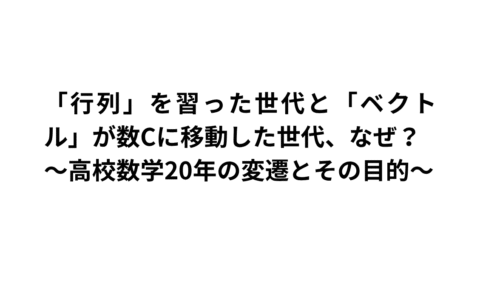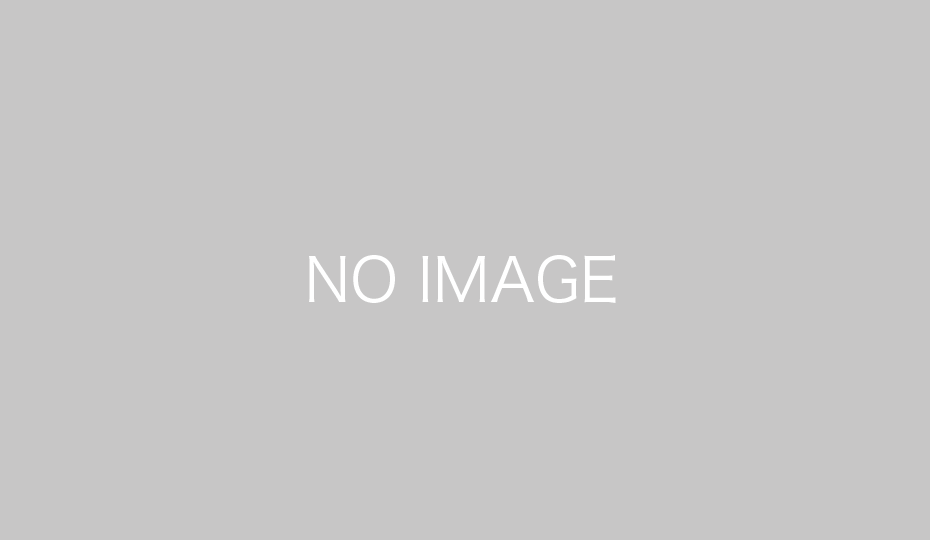問題
(1) $3x^2 – 2xy – y^2$ を因数分解すると、 [ ア ] となる。
(2) $x$ は実数とする。$|x| -2$ であるための [ イ ] 。 [ イ ] に当てはまるものを、次の 1~4 のうちから一つ選び、番号で答えよ。 1 必要十分条件である 2 必要条件であるが、十分条件ではない 3 十分条件であるが、必要条件ではない 4 必要条件でも十分条件でもない
(3) $\angle C = 90^\circ$ の直角三角形 ABC において、$AC=5, BC=12$ である。$\angle A = \theta$ とするとき、$tan \theta = $ [ ウ ], $sin \theta = $ [ エ ] である。
(4) 大人5人、子ども4人から3人を選ぶとき、選んだ3人がすべて大人となる選び方は全部で [ オ ] 通りある。また、選んだ3人に大人も子どもも含まれる選び方は全部で [ カ ] 通りある。
(5) $a$ は定数とする。次の7個の値からなるデータにおいて、中央値は16である。 $7, 9, 12, 22, 34, a-15, a+1$ このとき、$a = $ [ キ ] であり、このデータの四分位範囲は [ ク ] である。
解答
- (1) ア: $(3x+y)(x-y)$
- (2) イ: 3
- (3) ウ: $\frac{12}{5}$, エ: $\frac{12}{13}$
- (4) オ: 10, カ: 70
- (5) キ: 31, ク: 23
導入
この記事では、高校数学の様々な分野から基本的な問題を5問ピックアップし、その解法を丁寧に解説します。扱うテーマは、因数分解、必要条件と十分条件、三角比、場合の数(組み合わせ)、そして**データの分析(中央値・四分位範囲)**です。それぞれの問題の考え方の要点をおさえ、確実に解けるようにしていきましょう。
各問題の解説
(1) 因数分解
答え: $(3x+y)(x-y)$ 詳しい解説: $3x^2 – 2xy – y^2$ のような、複数の文字を含む2次式は「たすき掛け」を使って因数分解します。
-
先頭の項 ($3x^2$) と末尾の項 ($-y^2$) に注目する
- $3x^2$ を作る組み合わせ:$x$ と $3x$
- $-y^2$ を作る組み合わせ:$y$ と $-y$ (または $-y$ と $y$)
-
たすき掛けで中央の項 ($-2xy$) を作る 組み合わせをクロスさせて掛け算し、その和が中央の $-2xy$ になるものを探します。
x / y → 3xy × 3x \ -y → -xy -------------------- -2xy (間違い) x / -y → -3xy × 3x \ y → xy -------------------- -2xy (正解!)下の組み合わせで中央の項が作れたので、カッコに入れる際は横のペアを見ます。 したがって、因数分解した結果は $(x-y)(3x+y)$ となります。
(2) 必要条件と十分条件
答え: 3 詳しい解説: 条件の関係を調べるには、「p ならば q」と「q ならば p」がそれぞれ成り立つ(真)か、成り立たない(偽)かを考えます。
- 条件p: $|x| < 1$ → 書き換えると $-1 < x < 1$
- 条件q: $x > -2$
-
「p ならば q」を調べる(十分条件の判定) 「$-1 < x -2$ と言えるか?」を考えます。 -1と1の間にある数は、すべて-2より大きいので、これは成り立ちます(真)。 よって、「pはqであるための十分条件」です。
-
「q ならば p」を調べる(必要条件の判定) 「$x > -2$ ならば、必ず $-1 < x -2$ を満たしますが、$-1 < x < 1$ は満たしません。 したがって、これは成り立ちません(偽)。 よって、「pはqであるための必要条件ではない」です。
以上から、「十分条件であるが、必要条件ではない」が正解となり、答えは 3 です。
(3) 三角比
答え: $tan \theta = \frac{12}{5}$, $sin \theta = \frac{12}{13}$ 詳しい解説: 三角比を求めるには、直角三角形の3辺の長さが必要です。
-
残りの辺(斜辺)の長さを求める 三平方の定理より、$AB^2 = AC^2 + BC^2$ なので、 $AB^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ $AB = \sqrt{169} = 13$
-
$\tan \theta$ と $\sin \theta$ を求める $\angle A = \theta$ なので、この角を基準に考えます。
- 高さ (対辺): $BC = 12$
- 底辺 (隣辺): $AC = 5$
- 斜辺: $AB = 13$ 三角比の定義に当てはめます。
- $\tan \theta = \frac{高さ}{底辺} = \frac{BC}{AC} = \bf{\frac{12}{5}}$
- $\sin \theta = \frac{高さ}{斜辺} = \frac{BC}{AB} = \bf{\frac{12}{13}}$
(4) 場合の数(組み合わせ)
答え: オ: 10, カ: 70 詳しい解説:
-
オ(3人すべてが大人) 「5人の大人の中から3人を選ぶ」組み合わせなので、$ _5C_3 $ を計算します。 $$ _5C_3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10 \text{通り}$$
-
カ(大人も子どもも含まれる) これは「全体の選び方」から「条件に合わない選び方(すべて大人、または、すべて子ども)」を引くのが簡単です。
- 全体の選び方: 全員で9人から3人を選ぶので、$ _9C_3 $ $$ _9C_3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84 \text{通り}$$
- 条件に合わない選び方
- すべて大人:(オ)で求めた 10通り
- すべて子ども:「4人の子どもから3人を選ぶ」ので、$ _4C_3 = 4$ 通り
- 引き算する $$84 – 10 – 4 = \bf{70} \text{通り}$$
(5) データの分析
答え: キ: 31, ク: 23 詳しい解説:
-
キ(aの値を求める)
- データは7個なので、小さい順に並べたときの4番目が中央値です。
- 中央値は 16 ですが、わかっている数字の中に16はありません。よって、$a-15$ か $a+1$ のどちらかが16です。
- もし $a+1=16$ なら $a=15$ となり、データは
0, 7, 9, 12, 16, 22, 34。中央値は12となり不適。 - もし $a-15=16$ なら $a=31$ となり、データは
7, 9, 12, 16, 22, 32, 34。中央値は16となり、条件に合います。よって $a=31$ です。
-
ク(四分位範囲を求める) 四分位範囲は「第3四分位数(Q3) – 第1四分位数(Q1)」で求めます。 確定したデータ
7, 9, 12, 16, 22, 32, 34を使います。- 中央値: 16
- 第1四分位数(Q1): 中央値より小さいデータ
7, 9, 12の中央値なので、9。 - 第3四分位数(Q3): 中央値より大きいデータ
22, 32, 34の中央値なので、32。 - 四分位範囲: $Q3 – Q1 = 32 – 9 = \bf{23}$。
まとめ
今回は、高校数学の基本となる5つの分野から出題された問題を解説しました。
- 因数分解は「たすき掛け」を使いこなせるかが鍵です。
- 必要条件・十分条件は、ベン図や数直線で関係をイメージすると分かりやすくなります。
- 三角比は、まず3辺の長さを確定させ、定義に当てはめるのが基本です。
- 組み合わせの問題では、「余事象(条件に合わないものを引く)」という考え方が強力な武器になります。
- データの分析では、中央値や四分位数といった言葉の定義を正確に理解することが大切です。
基本的な計算ルールや定義をしっかり押さえて、様々な問題に応用できるように練習していきましょう。